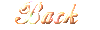川へ入っちゃいけないったら
『オツベルと象』宮沢賢治
【決シテ瞋ラズ】
白象は、誰かに呼ばれているような気がした。その声に従って森を抜け、山を降りて来てみると、十六人の百姓どもが、六台の稲扱器械を廻していた。
「のんのんのんのんのんのん」
単なる器械の音か、あるいはその音に百姓たちの祈りが込められていたのかは、わからない。
少なくとも白象には、
「のんのんのんのん(のんのん様、のんのん様)」
と、彼らが御仏に救いを求めている声に聞えた。
なにしろこの白象は、語り手の牛飼いが、
「白い象だぜ、ペンキを塗ったのでないぜ」
と強調する通り、正真正銘の白象なのである。
実は、白象というものには、特別な意味合いがある。
釈迦の前世時代を物語った多くの経典のなかに、『ジャータカ』というものがある。それによると、釈迦は前世で様々な身分、動物として生き、衆生のために身を捨てる菩薩修行を成した。その善因善果により、今世で悟りを得て仏陀となったというのである。
白い象は、釈迦の前身である動物としてしばしば登場し、その自己犠牲が、業に迷う人間を救うという話になっている。
このことから、白象は菩薩修行に勤しむ求道者を表すのだと解釈できる。したがって彼は、憐れな衆生のためにその身を捧げようと、常々心がけていたのだ。
菩薩修行については、法華経の『常不軽菩薩品第二十』に詳しいが、要するに、衆生のために我が身を犠牲にし、苦行を修めることである。そして、常不軽という字の通り、あらゆる者を常に礼拝賛嘆し、絶対に他を軽んずることをしない。
我が身にぶつけられるいかなる侮辱、嘲笑、迫害などにも、けっして瞋恚(しんに)を抱いてはならない。そうして耐え忍び、その身を捧げることによって、罪業に塗れた人間の内に潜む仏性を、目覚めさせるのである。
白象が「のんのんのんのんのんのん」に呼ばれてやってきたとき、オツベルはこの動物を儲けの道具ぐらいにしか思わなかったらしい。ところが、日が経つにつれ、白象には白象の目的があると見て取った。
普通の象ならば、ひどい仕打ちを受ければ、逆らうなり暴れるなりするだろう。しかし白象は、いたって素直である。何を言いつけても、文句ひとつ言わず、にこやかに働く。まして白い象だ。
「こいつは、常不軽菩薩修行をしているに違いない」
と悟るまでに、日数はかからなかっただろう。
なにしろオツベルは、語り手の牛飼いも太鼓判を捺すほど「頭がよくてえらい」のだ。それぐらいは簡単に推察できたに違いない。
牛飼いの言葉、
「じっさい象はけいざいだよ」
は、正確に言うと、
「白象はけいざいだよ」
であろう。あれだけ酷使して五把の藁ですむのは、やはり常不軽菩薩修行中の白象ならではのことなのだ。
【修羅の苦しみ】
そんなによく働く白象なら大事に扱うべきだというのは、働く側の理屈である。雇う側としては、そうは思いたくないものだろう。まして、そんなことを考えるはずないのが、オツベルのオツベルたる所以なのだ。
まず、労働の過酷さに反して、食事の量を減らし続ける。藁十把に始まり、八把、七把となるまで、そう日はかからない。その大義名分として彼は、
「税金が高い」
「税金がまた上がる」
「税金が五倍になった」
と、ことごとく税金のせいにする。おれのせいじゃないよ、政治のせいだよ、というわけである。
税金が上がるにつれ仕事量が増える一方、経済的事情から餌の量は減る。これもオツベルにとっては至極もっともな理屈なのだ。
ついでながら、実際に税金が高いか、また上がったかというのは、詮索するのも野暮である。そんなものは、白象をこき使う口実に決まっている。もし、本当だとしても、学校ぐらいもある仕事場に新式稲扱き器械を六台も持ち、十六人もの百姓を使っている彼が、簡単に打撃を受けるとは思えない。
白象は、そこまでを把握していた。さらには、それでこそ、自分が改心させようと見込んだ傲慢、強欲、無慈悲なオツベルであると、新たな熱意を燃やしたことだろう。なにしろ白象は、菩薩修行に邁進する求道者なのだ。
白象は、すべての人間に潜む仏性を確信し、オツベルをも礼拝賛嘆してきた。命じられた仕事は、喜んでやり、餌を減らされても文句を言わなかった。それどころか、常に感謝を捧げてきた。銅も鎖も、騙されたふりをしてつけている。
「うん、なかなかいいね」
と、さもうれしそうに言ってみせもした。入りたくもない檻にまで入り、嫌な顔もせずに一生懸命働いているのだ。
「ああつかれたな、うれしいな、サンタマリア」
などという言葉は、実は
「嘘でもいいからそう思い込め」
「無理強要を厭うな」
という、白象自身への訓戒であった。自分にそう言い聞かせ、自らに暗示をかけていたということだろう。
ひたすら、オツベルの内に潜む仏性が目覚めるのを、信じてのことである。常不軽の真髄をもって我が身を粉にし、オツベルに無言の問いかけをすることで、改心を促してきたつもりであった。
しかし、無理を続けられるほどの精神力と体力は、誰にでもあるものではない。むしろ、そんなものはないほうが普通だろう。
まして、これぐらいのことで易々と改心なぞしては、オツベルの名がすたるというものである。彼の仏性はいっこうに目覚めず、かえって理不尽過酷な扱いが増長する。
やがて、白象は笑わなくなった。そして、もの言いたげな「赤い竜の目」で、じっとオツベルを見下ろすようになる。
仏性だと? こいつにそんなものがあるのか。礼拝賛嘆だと? こいつにそんなことをして何になるのだ――
オツベルへの不信感は、修行そのものへの不信につながる。そして、白象の内なる瞋恚(怒り)の火種は、日ごとに大きくなっていくのだっだ。
白昼夢において白象は、いく度オツベルを踏み潰したことだろう。いくたびにわたって鋭い牙で、彼の喉を、胸を突き刺し、その肉を引き裂いたことだろう。オツベルの血しぶきで、自らの白い身体が朱に染まる悪夢にうなされる彼の耳には、どこかからか悪魔の声が響いてくるのだった。
「修行がなんだ」
「オツベルを潰せ」
「殺れ」
阿修羅の乱舞は、昼夜を問わず修行者を責め苛んだ。
この「赤い竜の目」には、オツベルも気づいていた。その色に反抗を見た彼は、まず「生意気な」と思ったに違いない。それから、鼻先で嗤った。
「初めのうちは善良ぶって嬉しそうに働いてやがったくせに、見ろ、もう化けの皮が剥がれてきやがったぜ。そのうち畜生の本性を表しやがるに決まってる。どこまですましていられるか、試してやれ。なあに、わざと力は減らしてあるんだ、たいしたことはできやしねえ。いざとなったら、撃ち殺してやるまでさ」
オツベルは、夜もひそかに象小屋近くへ行き、ものかげから白象の様子を窺った。そして、ある晩ついに、
「苦しいです。サンタマリア」
という言葉を聞きつけたのである。
オツベルのような人間にとって聖者というものは、おもしろくない存在である。悟りすまして自分を見下しているように思えるのだ。彼らによって、
「己の罪業を見よ」
と、見たくもないものを突きつけられるのが、癪にさわる。そうした「ゴリッパな者」が落伍する姿を見るのは、非常に愉快である。
かくして、白象の堕落を見たオツベルは、悪魔の勝利にほくそ笑むのだった。
ところで、人間はおおかた次の二種類に分けられる。相手が弱っていると、気の毒になり手を緩める者と、その弱さにつけこんでますます攻撃する者とに、である。
オツベルは、後者に当たるらしい。葛藤に苦しみ嘆く白象に対し、なおいっそうの瞋罵打害(しんめだがい)を加え、その反応を楽しんだのだ。
真の求道者ならば、オツベルの虐待をも試練として受け止めなければならないのだが、もはや白象には、そうした気力も体力もなかった。
悪魔の誘惑は、修行の最もつらいとき、修行者が弱りきった頃を見計らって、しのび寄ってくる。
ある晩、象は象小屋で、ふらふら倒れて地べたにすわり、藁も
たべずに、十一日の月を見て、
「もう、さようなら、サンタマリア」
とこう言った。
「おや、何だって? さよならだ?」
月がにわかに象に訊く。
「ええ、さよならです。サンタマリア」
「なんだい、なりばかり大きくて、からっきし意気地のないやつ
だなあ。仲間へ手紙を書いたらいいや」
月が笑ってこう云った。
「お筆も紙もありませんよう。」
象は細ういきれいな声で、しくしくしくしく泣きだした。
「そら、これでしょう」
すぐ眼の前で、可愛い子どもの声がした。象が頭を上げて見る
と、赤い着物の童子が立って、硯と紙を捧げていた。象はさっそ
く手紙を書いた。
聖者たるためには、あらゆる誘惑に勝たなければならない。悪魔の誘惑は、苦しい修行を投げだしたくなるような甘い言葉や、やさしげな誘い、もっともらしい理屈といった形で、修行者にまとわりつく。
とはいえ、修行を邪魔する結果になったにしろ、必ずしもその者に悪気があったとは限らない。月や赤衣の童子とて、そんなつもりがあったわけではないだろう。
おそらく彼らは、修行中である白象の立場を、本当には理解していなかったのではないだろうか。月などは、毎晩白象が
「ああ、つかれたな、うれしいな、サンタマリア」
などと言うのを聞いて、
「おやおや、あんなめにあってもうれしいのかい」
と、内心呆れつつも、そうかいとばかりに黙って聞いていたのだろう。
ところが、白象の「さようなら」を聞いたとたん、気の毒になったとみえ、重い口を開いたのだ。
「仲間へ手紙を書いたらいいや」
と、助言したのである。
一方、それに対する白象の気持ちは、
「お筆も紙もありませんよう」
という返事に表れている。
このまま菩薩修行を続ける気があるのなら、手元に筆や紙があろうとなかろうと、
「仲間の助けなどいらない」
と言い切ったはずである。にもかかわらず、筆記用具の有無にこだわるということは、
「お筆と紙があれば手紙を書きたいけど、ないからできないんですよう」
との嘆きに他ならない。その証拠に、赤衣の童子が硯と紙を持ってくると、ためらわずにそれを受け取り、いそいそと仲間へ手紙を書くのだ。
月や赤衣の童子は、世俗的な立場から白象に同情し、助かる道を勧めた。いわば、善意の存在である。たとえそれが修行の妨げになろうとも、俗なる者にとってそんなことは二の次なのだ。なんと言っても、無事が一番なのである。
つらさのあまり、自らの使命と立場を忘れた白象は、ついよろよろと月や赤衣の童子の善意に甘えてしまったのだ。
【瞋恚の噴火】
白象が手紙を書いた時刻は不明だが、午後八時か九時としてみる。その手紙を持って赤衣の童子はすぐ出発した。そして、歩きとおして山に着いたのは、昼どきである。つまり、オツベル邸から仲間の象たちがいる山の森までは、徒歩で十五、六時間ほどかかることになる。
ところが、手紙を読んで奮起した象たちがオツベル邸の近くまで来たときは、ちょうど一時半だった。「昼どき」を十二時とすれば、象軍団は、本来十五、六時間もかかる距離を、わずか一時間半で爆走してきたことになる。なるほど、「汽車より早く」やって来たのだ。
この象軍団は、まさしく善意の塊というべきものである。白象は「助けてくれ」と書いただけで、特にオツベルをどうしろとは、何も言っていない。しかし、この威勢のいい象たちは大奮発して、
「オツベルをやっつけよう」
と、立ち上がったのだ。
さあ、もうみんな、嵐のように林の中をなきぬけて、グララア
ガア、グララアガア、野原の方へとんで行く。どいつもみんなき
ちがいだ。小さな木などは根こぎになり、藪や何かもめちゃめち
ゃだ。グワアグワア グワア グワア、花火みたいに野原の中へ
飛び出した。それから、なんの、走って、走って、とうとう向う
の青くかすんだ野原の果てに、オツベルの邸の黄いろな屋根を見
つけると、象は一度に噴火した。
かくも盛大に激怒するところをみると、仲間の象たちは、菩薩修行の身ではないらしい。このとき彼らは、どんな目をしていたのだろう。やはり「赤い竜の目」だろうか。
いずれにしろ、彼らの怒りは、まさしく白象の内なる瞋恚の炸裂であった。白象の深層で「赤い龍」が首をもたげはじめたとき、彼はすでに柔和な菩薩修行者ではなくなっていた。怒りのとぐろを必死で抑えこんでいる激しい修羅の虜と化していたのだ。
こう考えてみると、白象の
「苦しいです、サンタマリア」
は、栄養失調や過労のせいばかりでなく、心中渦巻く瞋恚のマグマを抑えるのが苦しい、という意味もあったに違いない。
堪えに堪え、憤懣、無念、屈辱などの入り混じった涙を流す白象の内部で、「赤い竜」は、「グララアガア、グワア、グワア」の雄叫びを押し殺していた。それがついに表に向かって噴火し、激しい阿修羅が猛威を振るう。
ところがどうして、百姓どもは気が気じゃない。こんな主人に
巻き添いなんぞ食いたくないから、みんなタオルやハンケチや、
よごれたような白いようなものを、ぐるぐる腕に巻きつける。降
参をする印なのだ。
「こんな主人」とは、どんな主人か。オツベルは白象に対して酷い扱いをしたが、百姓たちにとっては、どのような主人だったのだろう。
百姓たちを働かせつつ、自分は何もせずにその辺をうろつき、ご馳走を食べるような主人ではあった。しかし、これぐらいなら、階級制度が残る時代の地主として、特に非道とは言えまい。オツベルが彼らを虐待したということは、本文には見られないし、無理に汲み取る必要もないだろう。
それ以上に気にかかるのは、この百姓たちの態度である。彼らは、常に我が身の保身を怠らない。
白象がやってきたときも、
「かかり合っては大へんだから」
と知らぬ顔を通し、白象が酷使されているのに同情した様子もない。いや、そればかりか、白象がおとなしいとわかるや、寄ってたかって虐め、ストレス解消の捌け口にしたかもしれない。他に楽しみもない百姓たちにとって、恰好の餌食だったに違いないからだ。しかも、主人の目が白象に向けられてさえいれば、自分たちが何か少しぐらいしくじっても、目立たずにすむ。
そうして、いざオツベルの身が危なくなると、
「こんな主人に巻き添いなんぞ食いたくない」
と、さっさと降参して身の安全を図るのだ。
敵に囲まれた挙句、特に酷使した覚えもない百姓たちにさえ背かれたオツベルは、たった一人塀の中で叫ぶばかりである。頼りになるのは、六連発のピストルだけだが、それとて象の堅い表皮には、なんの効も成さなかった。
さあ、オツベルは射ちだした。六連発のピストルさ。ドーン、グ
ララアガア、ドーン、グララアガア、ドーン、グララアガア、とこ
ろが弾丸は通らない。牙にあたればはねかえる。一疋なぞは斯う言
った。
「なかなかこいつはうるさいねえ。ぱちぱち顔へ当たるんだ。」
オツベルはいつかどこかで、こんな文句を聞いたようだと思いな
がら、ケースを帯からつめかえた。
実は、これはオツベルに与えられた最後のチャンスだった。似たような文句を白象が言った日のことを、このとき思い出せばよかったのだ。そもそも白象はなぜオツベルのもとへ来たのか。なぜ、酷使されても抵抗しなかったのか。
象が本気で怒れば、この通りのすさまじき威力を発揮する。ピストルの弾などは籾と同等、ましてオツベルごときを踏み潰し、ふっ飛ばすぐらい、なんの手間も力もいらない。
白象の常不軽菩薩修行が、実は自分に改心を促していたのだと、もしここで気づけば、彼は死なずにすんだかもしれない。たとえ命を落としても、悔い改めによって魂は浄化されただろう。
しかし、この期に及んで、そんな感傷に浸りなぞしないのが、オツベルのオツベルたる所以である。彼は最後のチャンスをも逃してしまった。生涯、醜い魂を持ち、悪人として生きたことになったのだ。彼に同情する者は、誰もいない。考えてみれば、憐れな存在である。
たぶん象たちにしても、オツベルを殺すつもりではなかったのだろう。その辺のものを派手にぶち壊し、恐怖に陥れてすませる予定だっただろう。塀をのり越えてどさっと落ちたら、たまたまオツベルがその下敷きになっていただけである。
「おや、あんた、そこにいたの」
と、象たちのほうで、驚いたほどだろう。
ところで、作中、語り手の牛飼いは、何度もオツベルを称賛する。冒頭からして、
「オツベルときたら、たいしたもんだ」
と、大いに持ち上げている。たぶんオツベル自身も、
「おれは、たいしたもんだ。えらいのだ」
と思っていただろう。自信と誇りが嵩じると、「慢」に陥る。「慢」とは、法華経でいう驕りの心である。オツベルは、自らの慢に気づくこともなく、そのせいで身を滅ぼした。
つまり、「えらい」ということが、破滅の元凶だったのである。
白象は、そのことをオツベルに気づかせるべく、身をもって問いかけてきたつもりだった。
【濁流に呑まれた菩薩】
初めてオツベル邸に来たとき、白象は稲扱器械からはね飛んでくる籾を浴びながら、
「ああ、だめだ。あんまりせわしく、砂がわたしの歯に当たる」
と言った。今となってみれば、これは白象の挫折の予感であった。この時点で、自分の力量を見定め、引き返せばよかったのだ。そうすれば、オツベルは少なくとも死なずにすんだ。
なお、物語中、オツベルが自分の罪を悔い改めなかったからといって、彼が腐敗の徒であるとは言い切れない。あと一週間、いや、あと五日、白象が忍耐を続けていれば、改心の兆を見せていたかもしれない。
オツベルとて、攻撃されれば反撃に出るだろう、ますます荒れ狂うだろう。彼の改心のチャンスを奪ったのは他でもない、仲間に救援を頼んだ白象自身である。
あまつさえ、自分が一人で暴れまくって、ぶち壊したのならまだしも、おめおめと仲間の助けにすがり、仲間の手を汚させたのだ。卑怯この上ない。白象の挫折感と罪悪感はいっそう募る。
しかし、仲間たちは失意の白象に対して非常にやさしい。なに一つ失敗を責めず静かに歩み寄り、鎖と銅をはずしてやるのだった。
「まあ、よかったね、やせたねえ」
仲間の言葉は、暖かい労りに満ちている。彼らは、無残な死に方をしたオツベルのことなど、もうきれいさっぱり忘れているのだ。そして、白象の挫折感に含まれる惨めさも罪悪感も、理解していない。ひたすら白象に同情し、助かったことを喜ぶばかりである。
仲間の思いやりに感謝しつつも、白象の孤独感と自責は深まる。オツベルを罪業から救えなかったのは、すべて自分の修行不足、忍耐不足のせいなのだ。
その苦しみは「白くない」他の象たちには、理解されないものである。賑々しく勝どきを上げる善意の仲間たちは、白象に言ったことだろう。
「これで安心だ。もう大丈夫だよ。よかったねえ」
自分の無事を喜んでくれる仲間に応えるべく、白象も笑ってみせなければならなかった。しかし、それは「寂しい笑い」にしかならなかったのだ。
【川へ入っちゃいけないったら】
臨場感あふれる語りを披露してくれた牛飼いが、突如口調を変えて叫んだ。
「おや、川へ入っちゃいけないったら」
この言葉を、白象に対するものと解釈する説もある。挫折感から身投げしようとする白象に投げかけられたとするものである。
ところがそれでは、語り手を牛飼いにした意味が、ほとんどなくなってしまう。やはりこれは、自分の牛に向けられた言葉だろう。主人が長話をしている間、退屈した牛は、川へ入ろうとしていた。あるいは、すでに足をぬらしていたかもしれない。
牛だって、水浴びぐらいしたいだろう。好きにさせてやればいいものを、牛飼いは慌てて止めたのだ。もちろん、危ないからである。
一見穏やかそうな川面も、底はどうなっているかわからない。突然深くなっていたり、濁流が渦巻いていたり、泥沼があったりする。充分に注意しなければ、足をすくわれる。しかし牛にそんなことはわからないだろう。したがって、危険なことは避けるがよいのだ。牛飼の懸念は、もっともである。
ところで、思慮が足りないために、うかうかと深みにはまった者がいた。あの白象である。
常不軽菩薩修行の「いかなる迫害にも、けっして瞋恚を抱かず耐え忍び、その身を捧げる」とは「攻撃しない」という意味で、無鉄砲猪突猛進を奨励するものではない。
かくの如く、多年を経歴して、常に罵詈らるるも、瞋恚を生さ
ずして、常にこの言を作せり
『汝は仏と作るべし』
と。この語を説く時、衆人、或いは杖木・瓦石を以ってこれを打
擲けば、避け走り、遠くに住りて、猶、高声に唱えて言わく、
『われ敢えて汝等を軽しめず、汝等は皆当に仏と作るべし』
岩波文庫『法華経(下)』坂本幸男・岩本裕・訳注より
つまり、身の危険に遭えば、さっさと「避け走り」、危害の及ばないところから見守り、声高らかに唱えるのである。必要に応じてまた近づき、危なくなったら、再び遁走する。このような柔軟な立場にいればよいのだ。
対して白象は、すっかりオツベル邸に居住してしまい、身の自由を失ってしまった。その相手にもよるが、迫害する者を正面に菩薩修行をまっとうするのは、至難の技であろう。
過酷な労働に耐え、体力を消耗させられながらも、オツベルの内に潜む仏性を信じ通せる、と白象は思った。そして居住を決意した。しかし、あえて危険な手段を選ぶからには、それに徹する覚悟と力量が必要となる。白象は、分不相応にして危険な手段を選んでしまった。彼は、自分の力量をわかっていなかったのだ。
証拠として、結果は惨憺たるものだった。瞋罵打害を受けつつ、相手の仏性を確信し、礼拝賛嘆に徹しようともがき苦しみ喘いだが、やはり成し得なかった。川の深みにはまり、濁流に呑まれた白象は、結局誰も救うことができず(それどころか殺し)、自身も菩薩の地位から転落したのであった。
さて、水浴びしたがっている牛を連れ戻しながら、牛飼いはこう言ったことだろう。
「無茶するんでねえぞ」
《了》
角川文庫『セロ弾きのゴーシュ』(昭和五十八年改版二十八版)収録
『オツベルと象』より